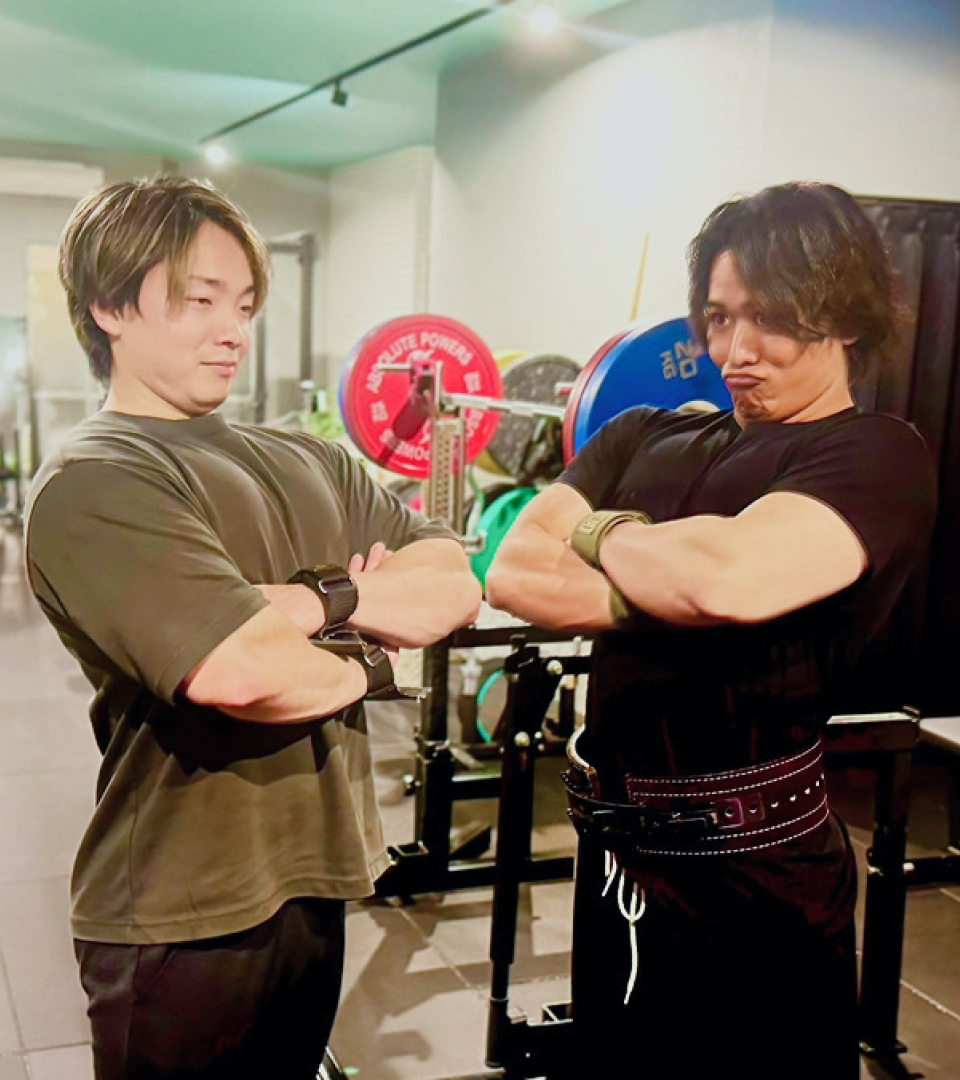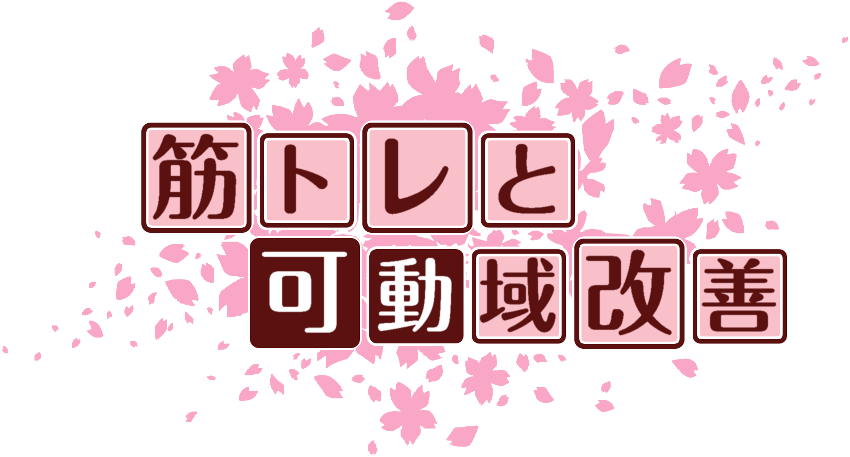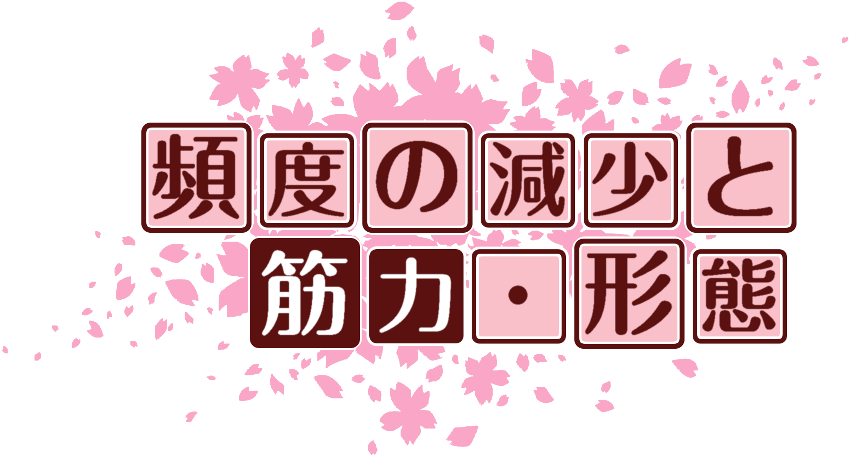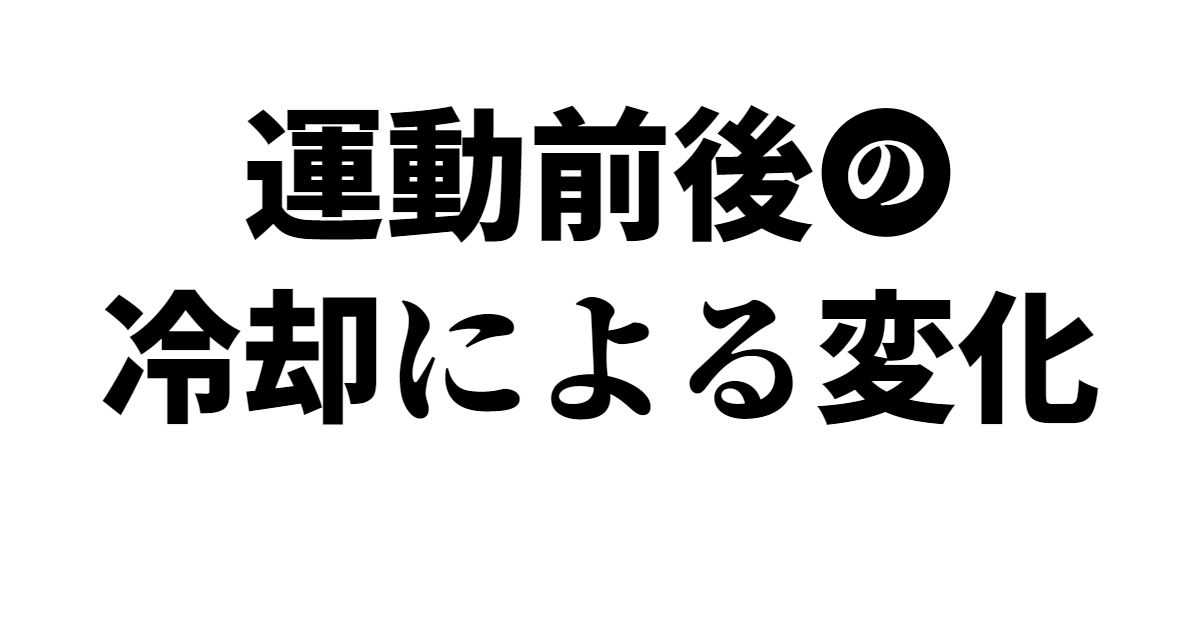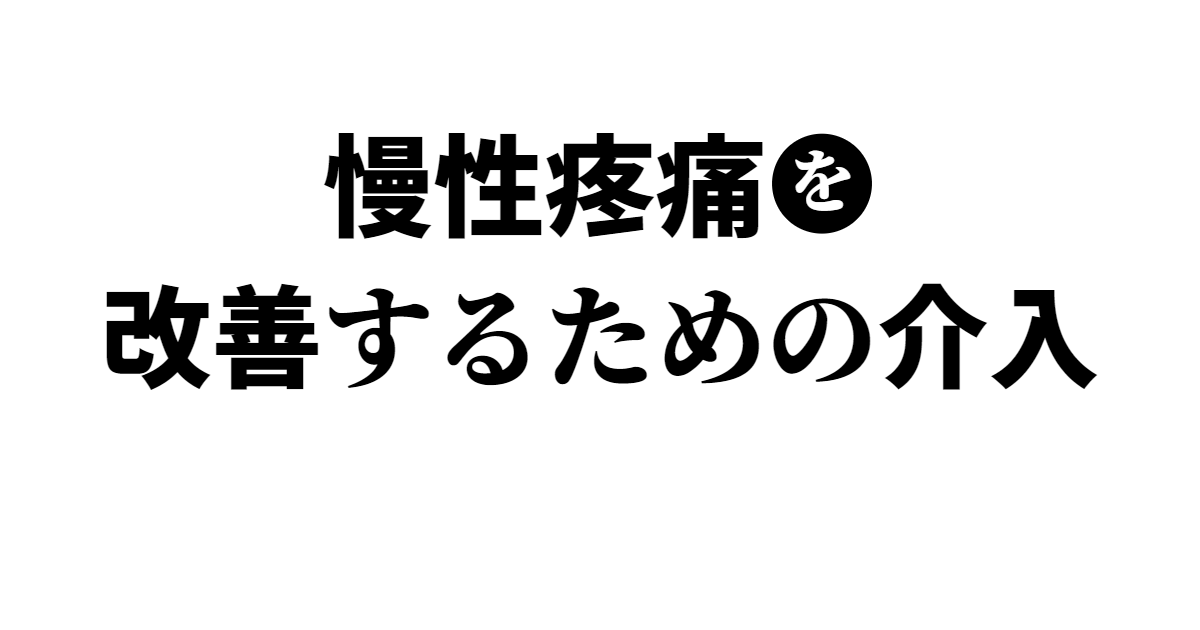2024.09.09
暑熱下での有酸素能力に影響について
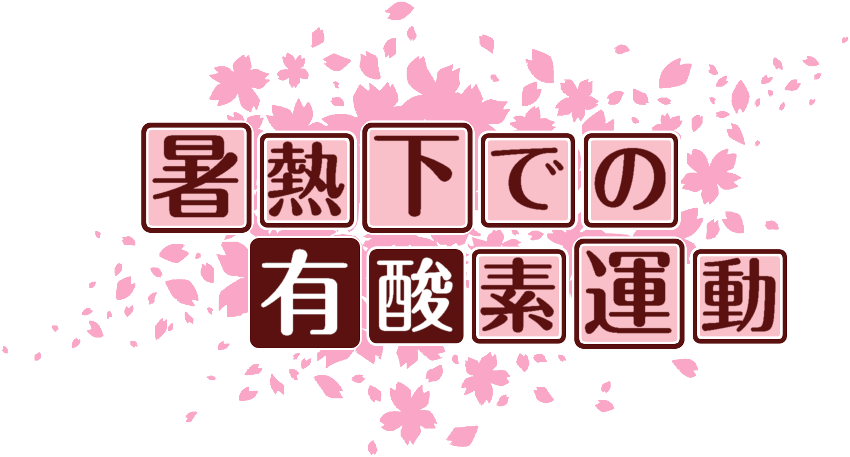
みなさまこんにちは。
パーソナルトレーナーの亀山です。
今回は臨界体幹温度ではなく、体幹から皮膚までの温度勾配の低下が、
暑熱下での有酸素能力に影響についての論文を引用していこうと思います。
論文
この研究の目的は、さまざまな環境条件において、漸進的なランニング中の体幹から皮膚までの温度勾配が、
意志による疲労に与える影響を判定することである。
二次的な目的は、暑い中でのランニング中に「臨界」体幹温度が意志による疲労を左右するかどうかを判定すること。
60人の参加者 (男性49人、女性11人、24±5歳、177±11cm、75±13kg) が研究を完了した。
参加者は、3マイルのランニングパフォーマンスに基づいて、特定の運動温度グループ (18°C、26°C、34°C、または42 °C) に
均一に層別化されました。
結果として、意志による疲労に到達するまでの時間は、18°Cグループと26°Cグループの方が
42 °Cグループよりも長かった(それぞれ58.1±9.3分と62.6±6.5分対51.3±8.3分)。
中間点および終了時点では18°Cおよび26°Cグループの中心から皮膚への勾配は、
42°Cグループと比較して大きかった 。
18°C グループの発汗量は、26°C、34°C、42°Cグループと比較してそれぞれ
3.6±1.3 gm(-2) min(-1) に対して7.2±3.0、7.1±2.0、7.6±1.7 gm(-2) min(-1) であった。
運動試験中、体幹温度と心拍数反応にグループ差はありませんでした。
現在のデータでは、開始時と終了時の体幹温度やベースラインの3マイル走行時間に差がないにもかかわらず、
18°Cグループと26°Cグループでは、42°Cグループと比較して、疲労困憊するまでの
走行時間がそれぞれ13%と22%長くなっていることが示されています。
この能力の差は、対流による熱放散に有利な環境温度による体幹から皮膚への勾配の拡大と、
部分的には発汗量の増加から生じていると考えられます。
結論として現在の研究のデータは、 高温下での有酸素能力の低下は、
体幹温度の臨界値よりも、体幹から皮膚の温度勾配の臨界値 (2.1 °C) の低下が主な原因であることを示しています。
これらのデータはさらに、胸部皮膚温度には約35.0~35.5 °C の上限「閾値」があり、
それを超えると皮膚灌流の増加または皮膚への血流増加の結果として
有酸素能力が低下する可能性があることを示唆しています。
まとめ
•皮膚温度は、能力が低下する前の閾値が約35.0~35.5 °C になる場合があります。
•有酸素運動能力と体幹から皮膚までの温度勾配は、運動耐性の最良の指標でした。
•体幹から皮膚までの温度勾配は、体幹温度と比較して疲労の指標としてより重要です。
暑い環境でのトレーニングは有酸素運動に影響を与え、能力の低下を招きます。
必よがある場合を除き、適温での運動の方が望ましいですね。
過去おすすめ記事
・暑熱順化のトレーニング適応について