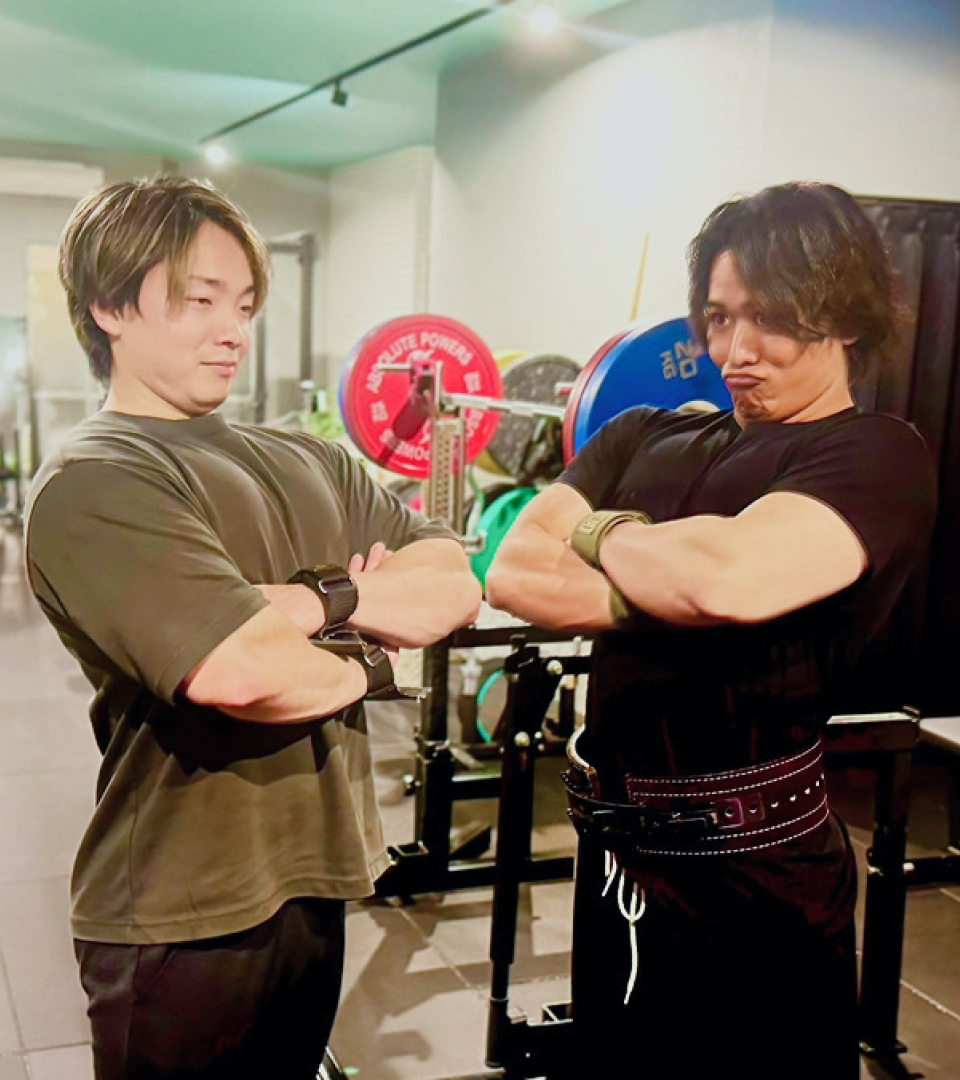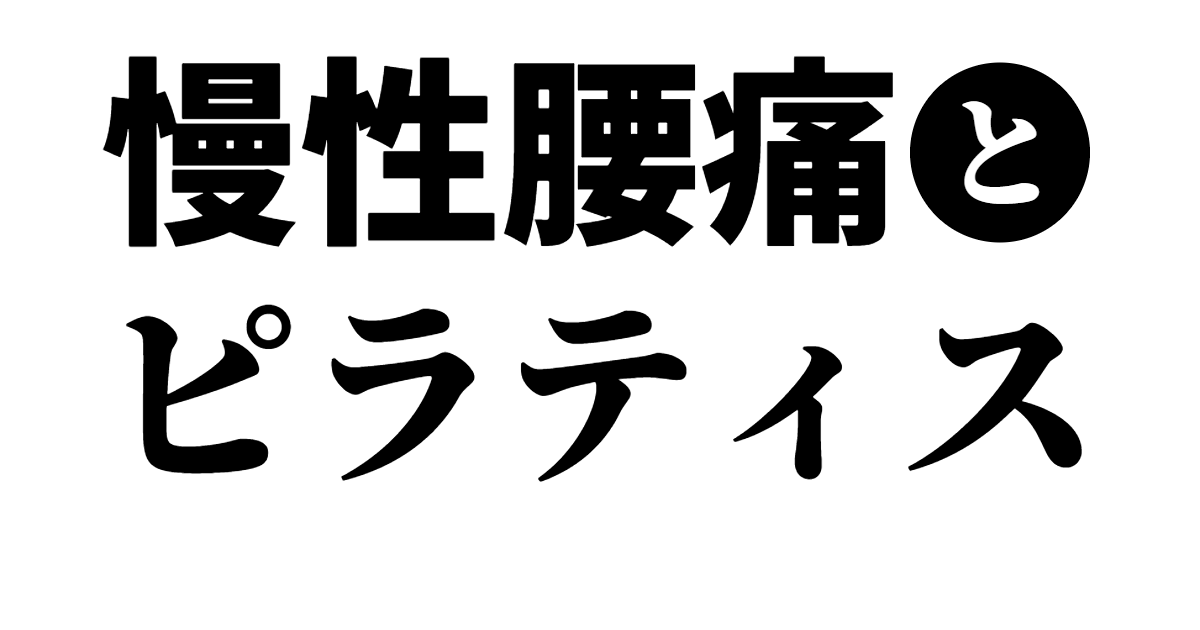2025.11.22
筋トレを継続する理由。ルーマニアの研究紹介

こんにちはTOMOAKIです。
最近24hジムに入会してせっせとトレーニングに励んでおります。
入会したジムでは非常に多くのトレーニーが週に複数回トレーニングされている様子です。
自分の場合は大会に向けた補強として、体をデカくしたくて筋トレを続けていますが
周りの方々がどのような理由で筋トレを習慣化しているのか、ふと気になることがあります。
そこで今回は、ルーマニアのボディビル・フィットネス実践者
60名を対象に行われたアンケート研究を紹介します。
参考文献:
Study on Aspects of Bodybuilding and Fitness Practitioners’ Motivation and Weight Training Routine
この調査では、身体づくりの目的、トレーニング中に感じる感情、
日々どのような習慣でトレーニングをしているのかといった、
興味深いデータがまとめられています。
日本のトレーニーにも通じる部分が多く、
読み物としても面白い内容だと感じました。
研究内容の紹介
この研究は、60名のボディビル・フィットネス実践者(競技者20名、非競技者40名)を
対象としたオンラインアンケートによって実施されました。
参加者の年齢は17〜59歳と幅広く、競技レベルやトレーニング歴も多様です。
アンケートでは、トレーニングの目的、使用する重量、
日々のルーティン、トレーニング中に感じる感情などが尋ねられました。
研究データには、実際に回答者がどの程度の時間トレーニングしているかの
個別記録が含まれており、60分や90分など、それぞれの生活リズムに合わせた
トレーニング時間が確認できますが、どれが多数派かといった
統計的なまとめは示されていません。
興味深い点として、すべての参加者が“muscular sense(筋肉の感覚)”を
感じていると回答したという結果があります。この「筋肉の感覚」は、
筋肉の収縮を意識したり、筋トレ後の変化を自身で認識できたりする感覚のことで、
研究ではその存在が筋肉の張り、収縮のコントロール、
筋繊維の見え方の変化などに関連すると説明されています。
また、研究の中では、最年少の17歳が「幸福感」を、
最年長の59歳が「充実感」を感じていると回答したことが紹介されており、
トレーニング習慣が心理的な側面にも強く影響していることが示されています。
競技者・非競技者ともに、トレーニングが生活習慣の一部として根づいており、
疲労やストレスへの対処として筋トレを継続している人も多いことが読み取れます。
考察
この研究から見えてくるのは、トレーニングが単なる身体づくりにとどまらず、
心理面にも大きな影響を与えているということです。
参加者の回答には、幸福感や充実感、モチベーションの向上といった
感情面の記述があり、筋トレが自己肯定感を支える
重要な時間になっている様子が伺えます。
これは、実際のパーソナルトレーニングの指導でも感じることで、
筋トレはわかりやすく扱う重量や数値、見た目の変化などの成果を実感でき
達成感は味わいやすい趣味?運動?の一つかなと感じています。
また、全員が「筋肉の感覚」を実感しているという結果は、
トレーニング経験を通じて身体への感受性が高まり、
自分の体と向き合う意識が強くなっているのではないかと思います。
これは、パーソナルトレーニングでもよく感じることで、
身体の変化に気づける人ほど継続しやすく、
モチベーションが安定しやすい傾向があります。
お尻が育って嬉しい!後ろ姿が変わった!服のフィット感が変わったなどなど。
研究では、競技者・非競技者いずれもトレーニングを生活に組み込んでおり、
年齢や職業を問わず「健康的なライフスタイルの一部になっている」ことが強調されています。
ここからは、世界的に見ても筋トレが生活習慣として
広がっていることが読み取れ、日本でも同じ傾向があると感じます。
まとめ
統計的なレップ数や比率は示されていないものの、
回答者全員が筋肉感覚を持ち、トレーニングを通じて
幸福感や充実感を得ている点は非常に興味深い結果でした。
競技者と一般トレーニーに共通しているのは、
筋トレがただの運動ではなく、生活の質や気持ちの安定に寄与しているということです。
私自身、日々の指導の中で「やった分が目に見えて返ってくるから楽しい」
という声をよく耳にしますが、この研究結果はその実感と一致しており、
筋トレが持つ心理的価値を改めて裏づけているように感じます。
今後もこうした研究を紹介しながら、
皆さんのトレーニングに役立つ情報を発信していければと思います。