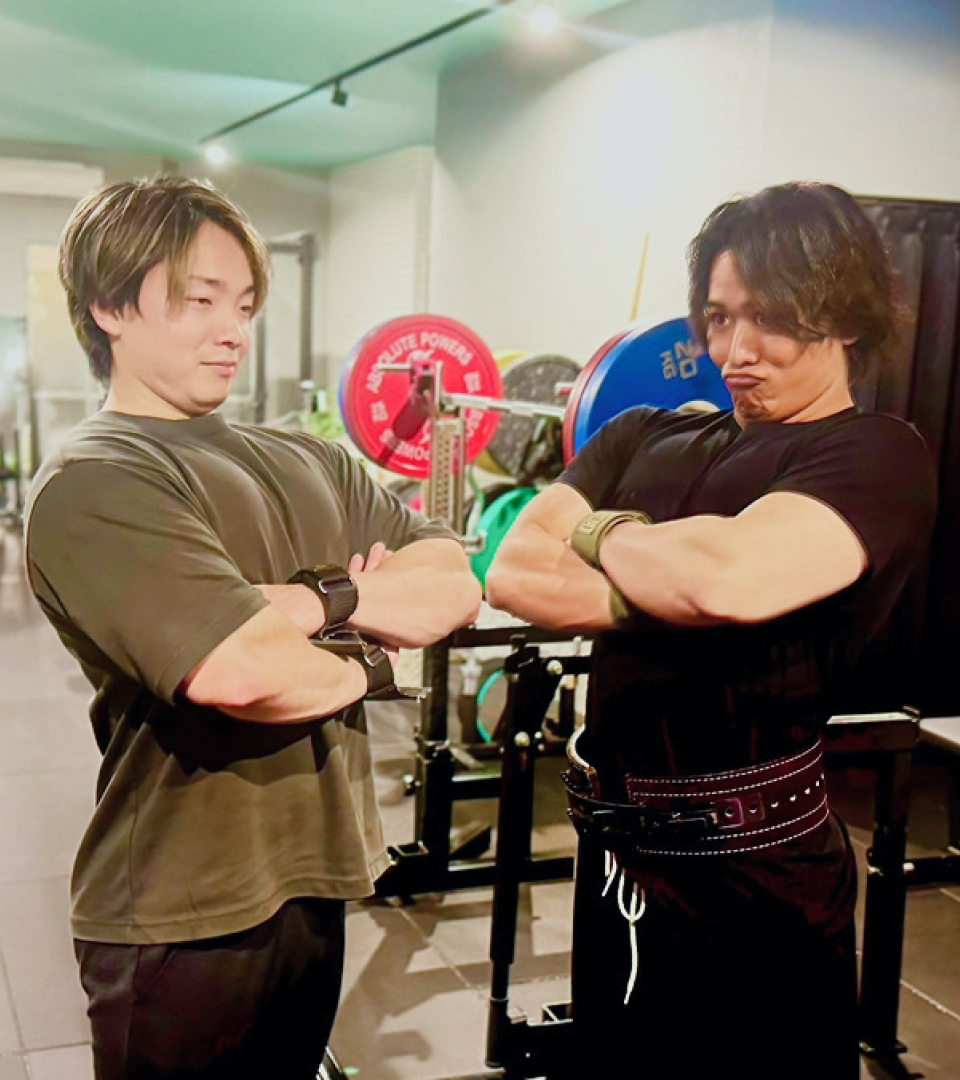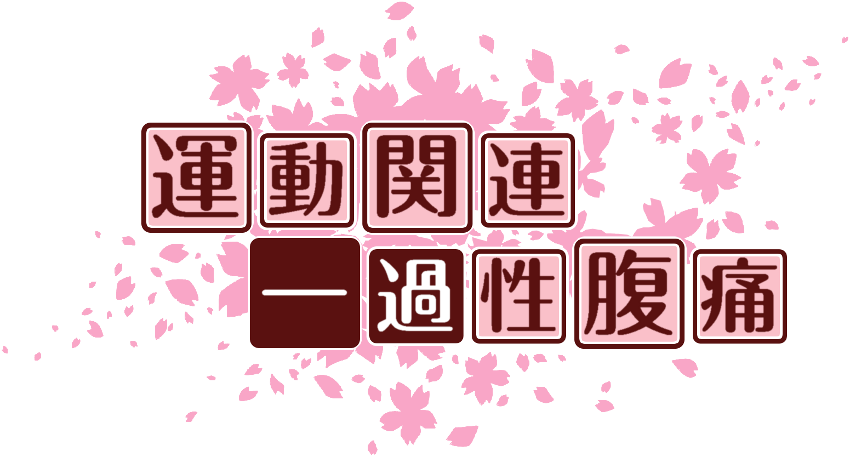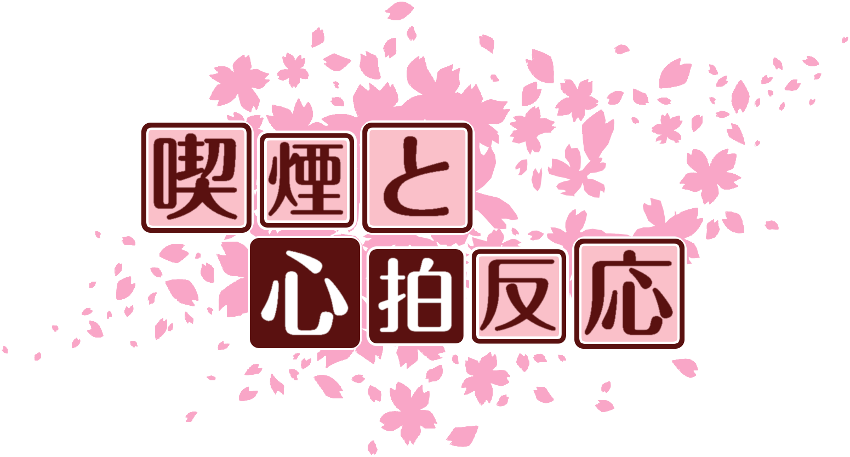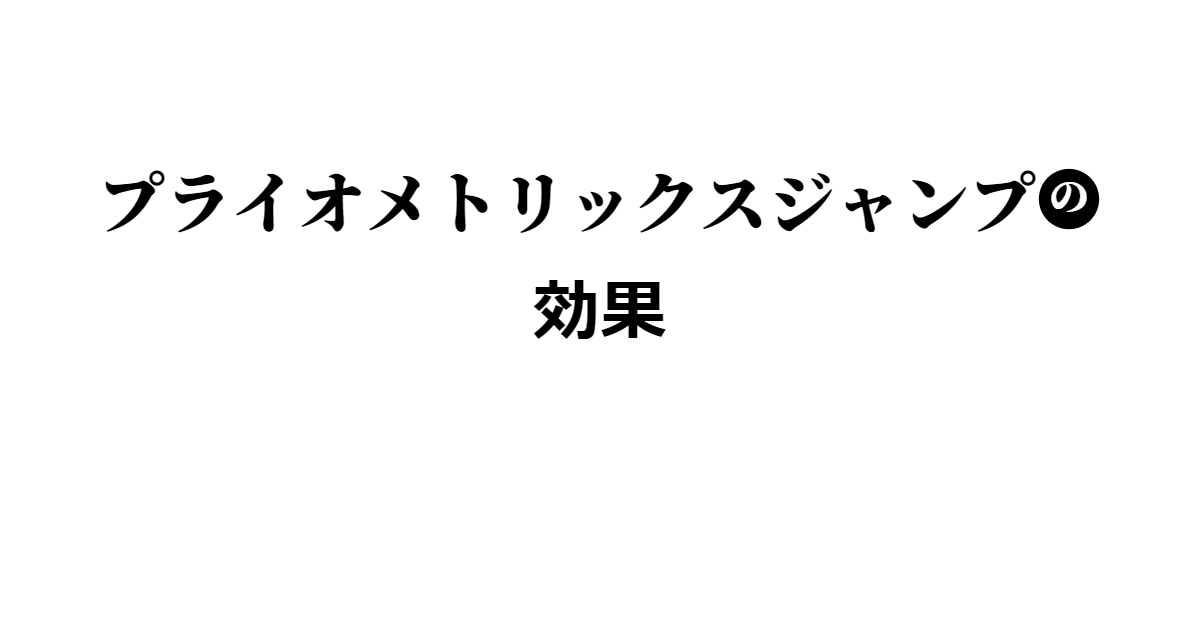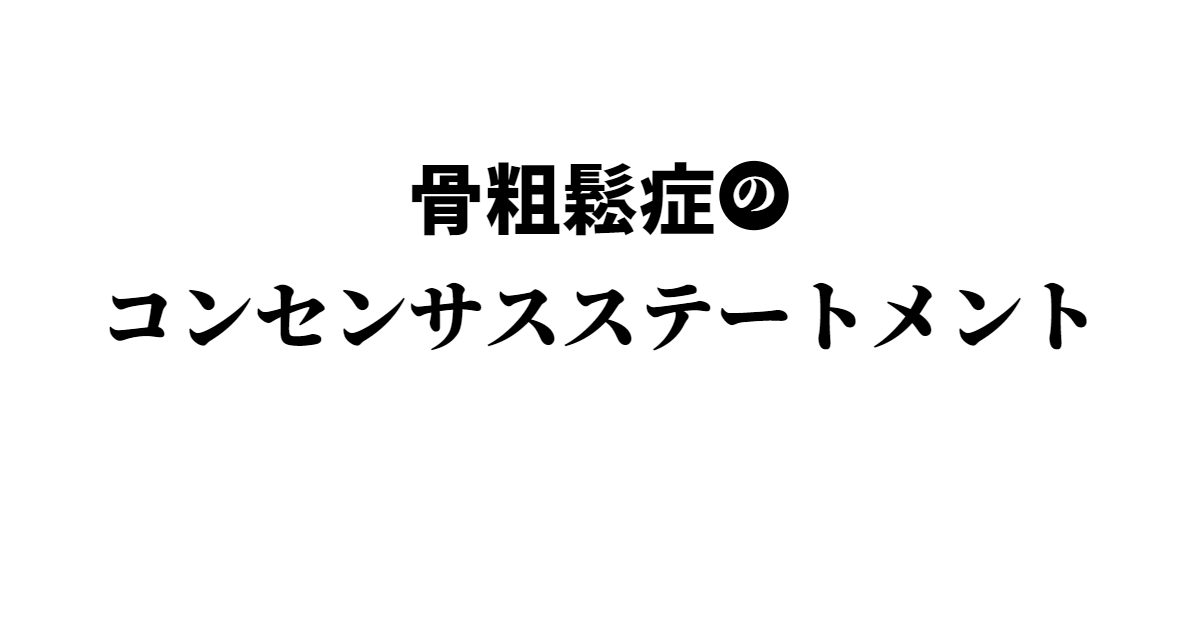2025.07.05
たんぱく質摂取総論2025
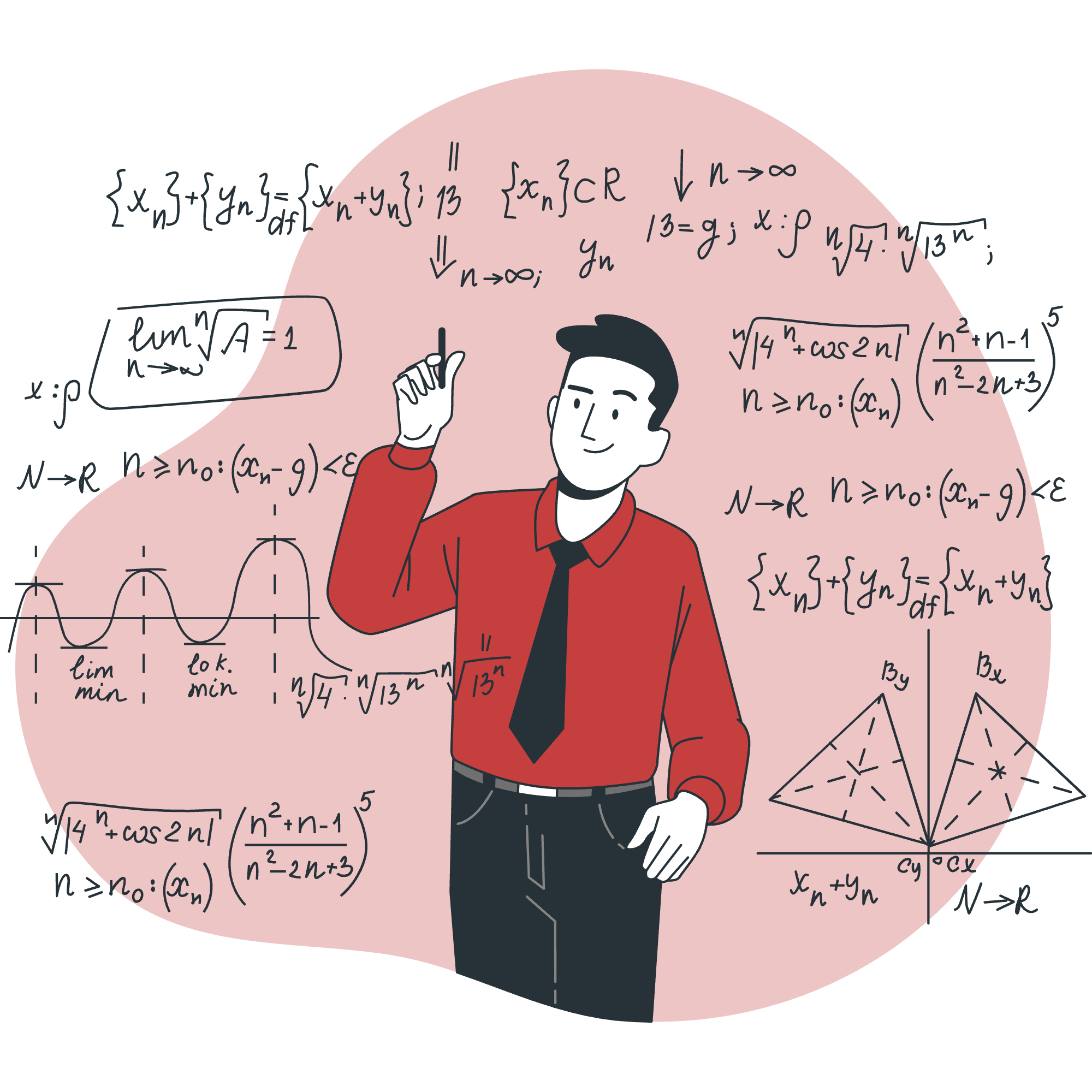
KONDOです。
2021年に執筆したブログから
もう4年も経ってしまいましたが
あまり目新しいたんぱく質摂取と筋肥大、
たんぱく質と除脂肪量の様な研究論文が
出てはいない様ではありますが、
過去のブログ様式から変わったため
再度執筆したいと思います。
「筋トレ後はたんぱく質◯g摂るべき」
「たんぱく質◯g摂れば健康」など
たんぱく質に限らずですが栄養素に対して
簡潔明瞭さを求めている人が多いです。
また、「たんぱく質が◯g摂れる」といった様な
商品がよく陳列されるようになっております。
一昔前は「たんぱく質の摂りすぎは腎臓に悪い」
とホエイプロテインを筆頭に現在の高齢者層が
特に言っていた個人的な印象がありますが
随分と世の中変わったなあ、と思います。
ボディメイクにおけるたんぱく質の考え方は
MPS(Muscle Protein Synthesis)の促進、
MPB(Muscle Protein Breakdown)の抑制
でありこれらを最適化する必要があるため
それすなわち筋肥大するためには、
減量時に筋肉を失わないためには、
たんぱく質をどのように扱うべきか、です。
たんぱく質
たんぱく質を摂取することで
たんぱく質単一で見た際のDITが高いため
ダイエットでは高たんぱく質がマスト
であるかのような投稿をよく見ます。
商品や料理に対して高たんぱくであるから
優れていると示唆するような投稿も。
たんぱく質が多ければ良いのか?
たんぱく質が多いとデメリットは無いのか?
たんぱく質が◯g無いと筋肥大しないのか?
たんぱく質の比率が通常では減量に不向きか?
など疑問はたくさんありますが
たんぱく質をDITとはじめとする
何かしらの効果を望んで摂取量を決めて良いのか?
多角的な目線が必要とされております。
現状のたんぱく質摂取量
現在の日本人のたんぱく質摂取量は
成人以上の男女で1日70g程度です。
また、5年毎に改定されている
日本人食事摂取基準の2025年版では
推定平均必要量(50%の人が必要量を満たせる量)は
18-64歳の男性で50g、女性で40g。
推奨量(97.5%の人が必要量を満たせる量)は
18-64歳の男性で65g、女性で50g。
つまり現在の日本人のたんぱく質摂取量は
国が定めるところの量よりも不足していません。
小麦たんぱくなどもありますし、
肉魚卵などのたんぱく質が豊富な食材を
摂っていなくてもちりつもで充足しているのでしょうか。
ラーメン1杯食べるだけでも
チャーシューや煮卵とか含めれば
小麦たんぱくも相まって
たんぱく質摂取量は30g近く行きますからね。
たんぱく質に対する関心が高まっているにも関わらず
実際のところ1950年代と同レベルにあります。
1990年代よりは摂取量は減少傾向にあり
それによる悪影響が何かしら生じている様な
好影響が出ているような
そんな感じではなさそうですね。
参考文献: 国民健康・栄養調査
コーチングのデータとして
ただ、当コーチングの指導データ的に
指導に入る以前の食事傾向が指し示すこととして
トレーニングや何かしらの運動をしていない人で
特に女性は1日あたりのたんぱく質摂取量が
30−50gの人が多く居るのは確かです。
週単位で見た時に
たんぱく質に限らず、総エネルギー摂取量が少ない
みたいな感じではあります。
平日は極端に少なくお休みの日は超過、など。
または、脂質と糖質の摂取に偏っているか、です。
最初からたんぱく質の摂取量が必要量・推奨量に
達している人の方が実際は少ない印象です。
実際日本人平均の摂取量として示されている
1日あたり70gの摂取量や国の指針を
初めから満たしている人はあまり多くないです。
これは女性の過剰なまでの痩身願望が
もたらしている食べないという習慣が
そうさせている様な感じもあります。
お腹が空いたら何か一応口にはするものの
食べない、気づいたら食べずに1日過ぎてた
みたいなパターンも実は少なく無いです。
逆に、トレーニングを週3−5くらい
行っているいわゆるトレーニーは
たんぱく質摂取量が過剰に多い傾向です。
当コーチングでも指導以前の食事傾向で
たんぱく質摂取量が200g超えていたりする
体重✖️3g超の摂取量の人など
総エネルギー摂取量の比率的に
たんぱく質が比較的多く占める形となっている
人が非常に多いと感じています。
たんぱく質とダイエット
先述しましたが
ダイエットにおいてDITの側面から
たんぱく質摂取量を多くすることで
それ自体のエネルギー消費量が見込める
ということで高たんぱく質が
推されることが多々あります。
実際リバウンドや体組成的に見て
除脂肪量に関して見るべきかと思います。
無論、たんぱく質摂取量を少々引き上げて
腹持ちやちりつもでDITの多さを見込むのも
戦略としては間違いでは無いことは
言うまでもありませんが、
どちらかというと減量時における
除脂肪量の低下を招かない様にするために
たんぱく質の摂取量を最適化する、
といったことが重要であると考えています。
たんぱく質を優先しすぎるあまり
脂質や糖質といった栄養素の量を
削りすぎてしまっている戦略は
あまり賢明とは言えません。
たんぱく質と除脂肪量
除脂肪量というのは
体脂肪以外の組織量のことであり
主に骨格筋量が反映されております。
つまりたんぱく質をちゃんと摂取し、
運動をしてあげることで
骨格筋量が維持されリバウンドしにくく
且つ痩せることに関して➕ですよね。
実際にたんぱく質と除脂肪量の関係を評価した
105本の信憑性高い論文を解析した
メタ解析がありますが
年齢や性別関係なく
たんぱく質摂取量を増やすことで
除脂肪量が増加すること、
体重1kgあたり1.3g程度までは
たんぱく質摂取量に比例して除脂肪量が増加
という結果が示されております。
参考文献:Dose-response relationship between protein intake and muscle mass increase: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
これは大体体重60kgの人であれば
1日78gのたんぱく質摂取量であり
現在の日本人のたんぱく質摂取量より
若干多い数字となっており
最近の世の中の過剰なまでのたんぱく質摂取の意識が
反映されている数値ではありませんね。
日本人の平均体重的に見れば
男性60kg半ば、女性50kg半ばくらいなので
1日100g以上の摂取は無さそうですね。
あとはこの数値に骨格筋量や
運動量その種類や頻度などに合わせて
変数として処理する必要があります。
実際この体重✖️1.3gという量でも
なかなか摂取できないという人も居ます。
人に合わせた食事戦略が必要であり
国の指針〜体重✖️1.3g摂取する様な
調整をしてあげれると良いです。
結論的に、たんぱく質の摂取に関しては
不足しないように意識することは重要ですが
ダイエットにおいて”過剰に”意識する必要はなさそうです。
たんぱく質と食欲抑制
たんぱく質摂取における
ダイエット・減量時におけるメリットがあります。
たんぱく質摂取は食欲に影響を及ぼす
消化管ホルモンの分泌に作用します。
簡単に言ってしまえば、
たんぱく質の摂取によって
食欲を減退させる作用があるということです。
長期的な食欲制御へのエビデンスは不明ですが
たんぱく質の摂取は食欲増進を促すホルモンである
血中のグレリンを減少させて
食欲を抑制する血中コレシストキニンと
グルカゴン様ペプチド1(GLP-1)を
増加させるということが
システマティックレビューにおけるメタ解析で
示されております。
つまりたんぱく質の摂取量をダイエット時に
若干多めに設定するということは
食欲抑制に繋がり体重減少の一助になる可能性が
示唆されております。
この様にDITだけの観点だけではない
ということを頭に入れておくと良いですね。
参考文献:Effect of short- and long-term protein consumption on appetite and appetite-regulating gastrointestinal hormones, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
活動量多い人の減量時にたんぱく質摂取量
実際のところ、減量における
たんぱく質摂取量が明確に検討されている
研究はあまり存在しないとされております。
エネルギー収支40%マイナスで
21日間、軍人を対象とした研究で
たんぱく質摂取量が体重✖️0.8gと比較して
体重✖️1.6g、体重✖️2.4gの時の方が
除脂肪量の減少率が低く、
✖️1.6gと✖️2.4gの有意差無かったとする
研究はあります。
参考文献:Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial
このように骨格筋量や活動量に合わせて
自分がどのくらいのたんぱく質を
摂取すべきなのか目的に合わせて
検討する必要があります。
たんぱく質に食欲減退作用があるとするなら、
増量期におけるたんぱく質摂取タイミングを
しっかりと検討する必要がありますね。
例えばトレーニング後から食事までに
あまり時間がないライフスタイルの場合、
トレーニング後にホエイプロテインなどを
摂取すると食事の際に必要な栄養素やカロリーを
摂りきれない可能性が出てきますからね。
たんぱく質と筋肥大
変数が必要と先述しましたが
筋肥大に対するたんぱく質摂取量は
長い間ずっと議論されております。
「体重の2倍」「体重の2倍だけじゃ少ない」
「体重の1.5倍で十分」
「たんぱく質は3時間おきに摂取すべき」
など様々であります。
現状、有力視されているのは
95%信頼区間含め最大体重✖️2.2gであるため
体重✖️1.62ー2.2gが広く知られております。
参考文献:A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults
この研究が指し示している内容と
当コーチングにおける筋肥大(増量期)における
たんぱく質量の指示はあまり相違なく
特に問題も生じていないと認識しています。
また先述の研究の減量時の除脂肪量維持のための
軍人の様な高活動?トレーニー?の様なハードな人の
体重✖️1.6g以上のたんぱく質摂取量というのと
一致しておりますね。
体重✖️1.6g〜というのがボディメイクにおける
たんぱく質摂取の1つの指針となりそうですね。
ライフスタイルに合わせて
たんぱく質摂取の仕方が異なるため
既製品ベースの方もいらっしゃり、
製品の成分表示上の誤差を考えて
下振れさせないように、という意図で
筋肥大目的なら体重✖️2.5gまで摂らせても
個人的には良いのかなと思いますが、
当コーチングにおいては滅多に居ません。
↑こちらの記事にあるように
筋肥大におけるたんぱく質摂取量が
多ければ多いほど比例して良い
というわけでは全くありませんので注意です。
競技特性別のたんぱく質摂取量
アスリートにおけるたんぱく質摂取量については
アメリカスポーツ医学会では体重✖️1.2−2.0g、
国際スポーツ栄養学会では体重✖️1.4−2.0g
が必要であるとガイドラインに示されています。
先述の体重✖️1.62gという数値も
これらの数値と適合しておりますね。
これらの数値からざっくりと
筋肥大のためには体重✖️2gといった
数値が導かれているのだと思われますし
正直言ってその認識で誤りではない、
とは思います。
たんぱく質の摂取タイミングと筋肥大
ここ最近では1日のトータルでの
たんぱく質摂取量が重要視されております。
よく巷で言われている
「運動後30分後がゴールデンタイム」
このタイミングでホエイプロテインを
摂ることが重要であるとする俗説があります。
しかしながらこのタイミングが
筋肥大に与える影響については一貫した結果が
得られていないことが現状であり、
運動したその日や翌日のたんぱく質摂取量に
着目することが重要であるとされております。
これはMPS(Muscle Protein Synthesis)が
筋トレによって刺激されてそれが48時間続く、
ということから考えられております。
平たく言えば、筋トレをした日と翌日は
ちゃんと意識してたんぱく質摂ろうねってことです。
トレーニーであれば週3ー5日は
筋トレをするでしょうから毎日ですね。
筋肥大目的や何かしらのアスリートであれば
最低でも体重✖️1.62g以上のたんぱく質を
1日で摂取したいということであります。
参考文献:
Effects of Timing and Types of Protein Supplementation on Improving Muscle Mass, Strength, and Physical Performance in Adults Undergoing Resistance Training: A Network Meta-Analysis
Is There a Postworkout Anabolic Window of Opportunity for Nutrient Consumption? Clearing up Controversies
Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans
Muscle-full effect
1日でのトータルたんぱく質摂取量で考える
という中でそれを何回に分けるのか?
も当たり前に議論になる点であります。
「1回あたり20g以上摂っても吸収しない」
「1回にたくさん摂っても無駄」
「小分けにして摂取した方が効率がいい」
など様々意見が飛び交っております。
実際に、よく聞く「吸収しない」
については誤った解釈となっており、
栄養学的な観点からすると
消化吸収というのは消化されて
血液に流れていくことを指しておりますので
厳密に言えば吸収されない
なんてことはありません。
筋肉の合成に使われるかどうかは別の話である、
という点が重要です。
なにも、たんぱく質というのは
筋肉だけに使われる栄養素ではありません。
髪の毛や爪など様々な細胞を構成する
材料となっており、
またそれでも余剰なたんぱく質があれば
エネルギー収支に伴い脂肪となりもします。
エネルギーを有しているとはそういうことです。
では、筋肥大に着目した時に
一体どのくらいの量を一回あたりで
たんぱく質摂取すればいいのか?
という部分が重要になってきます。
一回に100g程のたんぱく質を入れても
100gまるまる筋肉に使われる訳でもなく
じゃあどのくらいの量が最適解なのか?です。
Muscle-full effectという言葉をご存知でしょうか。
字の如くMuscleがfull(満腹)状態であるという意味です。
満腹状態であるとそれ以上とっても
筋肉の合成の応答が悪くなるのでは?というものです。
筋肥大のためにはMPSを高めたいわけですが
じゃあこのMPSを持続的に亢進させたいですよね。
ってことは断続的にたんぱく質を摂取してあげれば良いのでは?
と考えるのは自然であります。
実際、必須アミノ酸で静脈内投与ではありますが
血中アミノ酸濃度を一定に保つために
継続的に必須アミノ酸を投与したところ
30−60分でMPSが増加し、
60−120分でMPSがピークに達し、
120−360分でMPSがベースラインい落ち着いた
とする報告があります。
この研究報告をもとに3時間おきくらいに
たんぱく質摂取をしてあげることで
MPS応答を適切にし効率的では?
とされています。
参考文献:Latency and duration of stimulation of human muscle protein synthesis during continuous infusion of amino acids
1回あたりのたんぱく質摂取量
昔から
「1回あたり20gのたんぱく質摂取量がベスト」
「1回あたり40gで筋肥大が最大化」などなど
様々言われております。
体重70kgの人であれば
70✖️1.62gとした場合は113.4gであり
20gずつ摂る場合は6食ほどに、
40gずつ摂る場合は3食ほどに、ですね。
そして先述の頻度に照らし合わせて検討し
3時間おきに摂取するとなると前者20gの方が
科学的であると言えますね。
実際、体重✖️0.31gのたんぱく質摂取が
筋トレなどの運動を伴う場合に最大化されると
報告されております。
体重70kgであれば21.7gとなりますね。
個人的にも1回あたりのたんぱく質量は
大体30g前後となるようにしており
少食でもあるため必然的に小分けになり
自分が空腹になるタイミングが
大体3−4時間スパンであるため
私は自然と上記の頻度と量になっています。
また、私のコーチングでは基本的には
たんぱく質摂取の頻度をなるべく均一にしたいため
3食なら3食、5食なら5食で
同量くらいの分配になる様に指導しておりますが
特に指示を与えていない傾向を把握するための
記録とりの期間中は
夜の食事におけるたんぱく質摂取量が
他の食事タイミングと比較して遥かに多い傾向に
ある人がほとんどであります。
一般的にはたんぱく質摂取量が
どこかの食事タイミングで偏りが起きている
人が多い気がします。
実際、アスリート対象ではありませんが
3回の食事で1回あたり
たんぱく質摂取量が体重✖️0.31gする群と
朝食のたんぱく質量を減らし
夕食のたんぱく質量を増やした群に分け
12週間筋トレを実施した結果として
前者の方が除脂肪量が増加したとする
研究報告があります。
参考文献:
Maximizing Post-exercise Anabolism: The Case for Relative Protein Intakes
Evenly Distributed Protein Intake over 3 Meals Augments Resistance Exercise–Induced Muscle Hypertrophy in Healthy Young Men
ボディメイクにおける科学的なたんぱく質摂取
ここまでを整理すると
ダイエットや減量においては
除脂肪量の維持のためにも
体重✖️1.3−1.6g程の
たんぱく質摂取量が望ましい
筋肥大においては
体重✖️1.62−2.2g程の
たんぱく質摂取量が望ましいが
骨格筋量などの合わせて増減を。
筋肥大において可能であれば3時間おきに
たんぱく質摂取ができると望ましい
筋肥大において
1回あたりのたんぱく質摂取量が
体重✖️0.31gが望ましい
筋肥大において
基本的には毎食のたんぱく質摂取量が
均一であることが望ましそう
であります。
体重✖️0.31gした数値で
体重✖️1.62ー2.2gした数値を割って
その数分の食事回数ができると良い様です。
たんぱく質の種類と質
某タレントが
テレビで「世界では動物性ではなく
植物性たんぱく質が主流になりつつあり〜」と
言っていたのは記憶に新しい。基本的に学の無い人間は日本ではなく
諸外国を引き合いに出して
遅れているだ進んでいるだを話し出す。
過去記事にも記されておりますが
特に植物性が動物性よりも秀でている
とする感じではございません。
アミノ酸のロイシンがトリガー的なものであり
その含有量やアミノ酸組成的に見ても
むしろ普通に動物性たんぱく質の方が
筋肥大には良いかと思います。
特定のアミノ酸を添加して強化するなんて
また面倒なことを・・という感じなので
特に何かしらの思想がなければ
動物性たんぱく質の摂取でOKです。
たんぱく質摂取と危険性
では逆にたんぱく質摂取による
危険性は無いのか?という疑問が生じます。
私がトレーナーとして活動し始めたのは
13ー14年ほど前に遡りますが、
当時は中高年ー高齢者層の方達を中心に
「たんぱく質は腎臓に悪い」とする
俗説がかなり浸透していた印象です。
プロテインが筋肉増強剤の様なものだと
真面目に思っていた人も多く、
健康に悪いなどと思い込んでいる人が
わんさか居る時代でした。
特に腎臓に対して害があるというのは
一酸化窒素による求心性動脈管の
血管拡張による糸球体濾過量の増加や蛋白尿、
糸球体硬化がたんぱく質=腎臓に悪い
のイメージの起源であると考えられております。
個人的には実際は、もっとフランクに
腎臓機能が低下している人は
たんぱく質摂取を控えさせられるため
=たんぱく質は腎臓に負担をかけるという
認識になっている人が多いと思います。
参考文献:Chronic effects of dietary protein in the rat with intact and reduced renal mass
しかしながら現状の研究報告においては、
システマティックレビューにおいて
体重✖️3.3gまでのたんぱく質摂取量では
先述の憂慮されている悪影響が確認されず、
2型糖尿病患者を対象にしたコホート研究でも
たんぱく質摂取量が寧ろ低いと、
腎臓機能低下のリスクが増加されることが報告され、
健常者を対象にしたコホート研究でも
たんぱく質摂取量が低いと慢性腎臓病の発症リスクが
増加することが報告されております。
これらの観点から、たんぱく質が腎機能へ
悪影響をもたらすという明確な報告は無く、
具体的な数値も分かっていないため
これまでに挙げてきたたんぱく質摂取量内であれば
腎機能がそもそも低下していない健常者であれば
特に問題が無さそうだと言えます。
参考文献
Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis
Low-protein diet is inversely related to the incidence of chronic kidney disease in middle-aged and older adults: results from a community-based prospective cohort study
たんぱく質と色々
たんぱく質単体で摂取していくよりも
糖質と一緒に摂取した方がリカバリーが早そうです。
そこにクレアチンも足してあげると良さげです。
相乗効果をもたらしてくれそうです。
筋力向上においても体重✖️1.5gと
前述の数値に含まれておりますので
この辺りの数字は運動する人にとっては
マストと言っても過言ではなさそうですね。
満腹感は生じさせやすいものの
たんぱく質の質の悪さや脂質量など
考慮すべき点があるため推奨はしません。
増量期は食事量が減少しやすく
エネルギー摂取量が減少する可能性があるので
特に注意が必要ではありますが、
牛乳でホエイプロテインを割って、
そこにデキストリンとクレアチンが入れば
ポストワークアウトドリンクとしては
かなり優秀になる気がしますね。
基本的に1日あたりのたんぱく質摂取量が
充足されていればこういったアミノ酸ドリンクの
追加恩恵は特に無さそうですが、
味付け適度に飲みたければ飲めば良いのでは、
と思います。
睡眠中のMPBを抑制するためにも
睡眠前のたんぱく質摂取に焦点が当てられることが
ありますが、カゼインである必要性はありません。
こんな研究報告もあったりします。
私の個人的な考えとしても、
特に思想がない限りは動物性たんぱく質をメインにし
ビタミンCやビタミンEなどを
トレーニング後には摂りたくないです。
最近のホエイプロテインには付加価値のために
そういった栄養素を添加しているところが多く
なかなか悲しいですね。
まとめ
現状の研究論文をもとに色々まとめてみました。
今後新しいものが出てくるとは思いますし
あくまでこういう報告があるんだよ
みたいな目で見てもらえれば良いです。
個人的な感覚としても
前述の数値たちはわりかし理にかなっていて
かなり現実的な数値に近いと思います。
あとは個々人の体格やライフスタイルに合わせて
継続可能なたんぱく質との向き合い方を
検討していただければと思います。